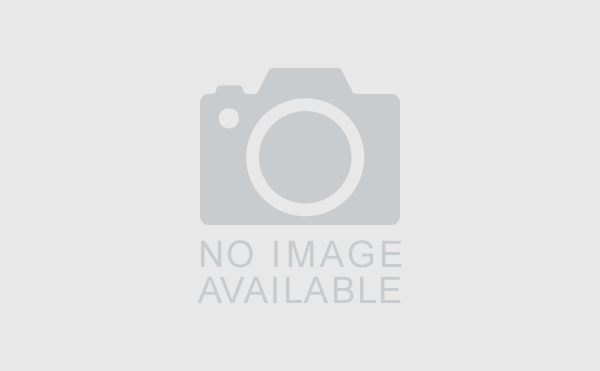【土壌分析】法令の話:土壌環境基準(溶出試験・含有試験)編

土壌分析に関わる法令は様々ありますので、それぞれの特性を把握していますと、分析項目や分析方法を選定する際に役立ちます。本コラムより不定期ですが代表的な法令について触れていきます。最初の回は、土壌環境基準について取り上げます。
なお土壌環境基準の詳細については、「土壌環境基準(環告46号) 溶出試験28項目」のページにて解説していますので、より詳しい内容を知りたい方は下記のページをご参照ください。本コラムでは押さえるべきポイントを簡潔に説明します。
土壌環境基準について
土壌環境基準は、「土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月3日 環境庁告示第46号)」にて定められています。環境基本法に定められる環境基準のうち、土壌の基準を定めたものとなります。
法令の告示番号から「環告46号基準(試験)」と呼称されることもあります。
土壌環境基準に基づく分析が用いられる代表的なケースは、以下のようなものがあります。
- 行政等の公的な機関から発せられる土壌調査命令に伴う事業
- 公共事業等における土壌の安全調査に伴う事業
- 建物の建築・解体において発生する残土の調査
- 土壌へ埋める・散布する製品の安全性の評価
- エコマークなどの各種認証を得るために行う安全性確認試験
- 不動産売買における土地の価値の算出のための調査
公的な事業にて用いられることはもちろんですが、最近では自主調査という形で民間での分析実施も少なくありません。また残土の排出や移動については、条例等で独自の規制を定めている自治体もありますが、この土壌環境基準をベースとして基準を定めるケースも多いようです。
土壌の分析=個体の分析となりますので、土壌以外のものの分析にも用いられることがあります。例えば土壌へ撒く肥料や調整剤などの製品、土壌に埋設処分する一部の廃棄物、などです。
土壌環境基準の溶出試験
溶出試験は、「対象の土壌から有害物質がどれだけ水に溶け出すか」を調べる試験です。土壌の汚染は地下水や雨水を媒介として汚染を広げる傾向が強いため、特に水に溶け出す量を重要視し、基準を定めています。周辺環境に対する影響への指標といえます。
土壌環境基準の溶出項目は28項目あります。土壌の分析において他によく挙がる土壌汚染対策法(土対法)の溶出項目は27項目であり、この違いは何なのかという問合せをいただくことがあります。
実は土壌環境基準の溶出28項目と、土対法の溶出27項目のうち、27番目までは全て同じものです。土壌環境基準にのみ、「1,4-ジオキサン」という物質が28番目に存在します。つまり1,4-ジオキサンの有無が、土壌環境基準溶出28項目と土対法溶出27項目の違いとなります。
土壌環境基準の含有試験
含有試験は、「対象の土壌そのものにどれだけ有害物質が含まれているか」を調べる試験です。土壌環境基準では農作物の育成(特に米)への影響に重点を置いて基準値を定めています。そのため対象は農用地(特に田)のみ、項目数は3と非常に限定的なものとなっています。
3項目のうち「カドミウム」については、収穫された米に対する基準となっていますので、実質的に土壌に対する基準が定められているのは、「銅」と「ヒ素」の2項目です。
本来は農用地限定で係る基準ではありますが、地方自治体の条例等によっては、銅とヒ素の含有量も分析を義務付けているケースも見受けられます。「農用地ではないから不要」とはならない可能性もありますので、その点に注意が必要です。
土壌分析のお問い合わせ・お見積依頼
土壌分析のお問い合わせ・お見積依頼はこちらからどうぞ。